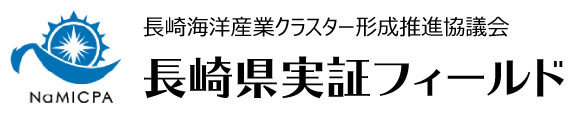海底地形調査
海底地形調査(五島市椛島地先)
五島市椛島沖の実証フィールド海域における詳細かつ面的な地形・地質を海底地形調査、底質分布調査および海底下地質調査により把握し、実験や研究の場として有意義な情報を確保することを目的に調査を実施した
観測場所 長崎県五島市椛島地先(椛島南東沖 3.4km×0.8km 矩形海域)
調査期間 2016年1月21日 ~ 2016年1月28日
調査項目一覧表
| 調査項目 | 目的 | 調査方法 | 調査数量 |
| ①海底地形調査 | 海底形状と傾斜勾配の把握 | マルチビーム測深 | 3.4km×0.8km,0.05km間隔 (総延長距離※:35.3km) |
| ②底質分布調査 | 海底底質(岩盤・砂泥の判別)の把握 | サイドスキャンソナー | 3.4km×0.8km,0.05km間隔 (総延長距離※:35.3km) |
| ③海底下地質調査 | 海底下地質(堆積層の層厚)の把握 | 地層探査システム | 3.4km×0.8km,0.10km間隔 (総延長距離※:67.7km) |
調査方法
① 海底地形調査
測位はGNSS(DGPS)、測深はマルチビーム測深機(Sonic2024)を用いて海底地形調査を行った。調査海域に未測深域が発生しないよう実施した。測線間隔100m、スワス幅90°、ラップ率20%に設定し、等深線図及び鯨観図、勾配図を作成した。
② 底質分布調査
サイドスキャンソナー(System3900)を船尾から曳航し、海底面から30~40m程度の高さを維持しながら海底地形調査と同一測線を調査し海底底質図及底質モザイク図を作成した。
③ 海底下地質調査
椛島沖の実証フィールドは、水深が深いところで100m以上あることから、探査水深に適応した、電磁誘導式地層探査機(ブーマー Model AA301)を用い50m間隔×17測線で実施した。音波探査は、調査船から発振機、受振機を曳航しながら、海底に向けて一定間隔で音波を発振し、海底面や海底下の地層の境界で反射した音波を観測し、地層の形状や重なり、連続性等、海底下の地層状況を調べる方法である。